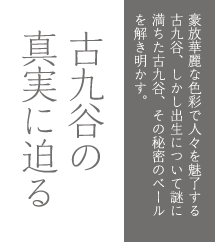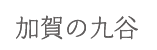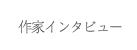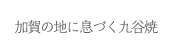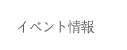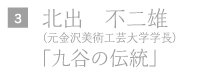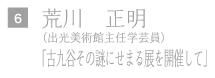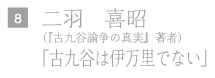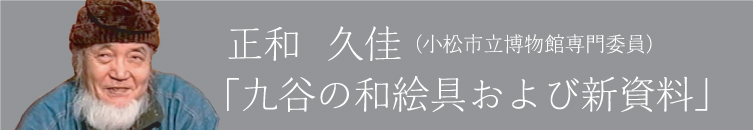
- 司会 >
- 今回は、小松市立博物館専門委員の正和久佳さんのお話をお送りいたします。正和さんは九谷の地で、その九谷焼の絵の具のもとを実際に採取、研究なさっているそうですね。
- 中矢進一氏 >
- そうですね、正和さんは郷土史家でもあるんですけども、九谷の実作者でもありましてね。実際に九谷焼の制作に携わっておられる、それだけに絵の具については詳しいんですが、九谷村に何度も何度も調査されまして、ついにそこでですね、従前からいわれている朱石、赤の絵の具のみならず黒の絵の具ですね、こういったことも発見されて実際に実験的に絵付けをされたりして、積極的に絵の具から古九谷に迫っておられますので、そこの辺りをみなさんに紹介できたらと思うんですね。
- 司会 >
- それではVTRをご覧ください。
対談
- 中矢進一氏 >
- 九谷の朱田と朱石の話をしていただきたいんですけど、九谷の赤の原料が九谷の方で採れるという話、実際のものを皆さんにお見せしていただきながらお話をしていただければと思います。
- 正和久佳氏 >
- 九谷赤、これが九谷から採取しました。昔から朱石って言われます、赤い石を材料にした赤です。昔から九谷に赤がある、朱石があるというのは、江戸時代の『茇憩(ばっけい)紀聞』】という本に書いてありますので、絵の具を自分で調整して絵を付けている作家たちは、明治頃から山に採りに行きまして、実際に畑に行きますと、朱田というのがありまして、そこにこの程度の石は点々とありましたので、みんな持って帰って絵の具にするんです、私もそうなんですが始め絵の具にするんですが、赤にならないんですよね。
無くなったのか畑が違うのかと諦めていたんですけど、たまたま縁がありまして、今の吉田屋の工房跡っていうのを発掘するきっかけを得まして、そこが掘り返されたものですから、下に埋まっていたものが上にでてきたわけですね。そうするとこういういいものが、たぶん踏みつけられたり、土砂に流されたり選別されたりいろんなことしておりますから、発掘ですから、量は少ないんですけどいいものがあって、やっぱり間違いなく九谷古窯と吉田屋の窯の窯跡のあの前の広場が朱田だったいうのが裏付けられましたし、『茇憩紀聞』の記述も間違っていなかったという裏付けにもなりました。それから、古九谷の時代にあそこの地元の足下から材料、原材料があったといい証にもなりましたのでよかったなというふうに思って、これをなんとかやっぱり活用できればなという風に思っています。
- 中矢進一氏 >
- それでは次に先ほどの朱石、すなわち九谷焼の赤の上絵の具の原料の話に引き続きまして、今度は九谷焼の上絵の具の黒の絵の具ですね。いわゆる呉須と言われるもの、こちらも九谷の方で正和さんが採集されて実験も、試し焼きもされておられます。そこのところ少し皆さんに説明して下さりますでしょうか。
- 正和久佳氏 >
- 呉須の話はね、さっきの赤よりもっとドラマチックでしてね。朱石を採取しに行って、発掘も終わって埋め直されてますので、何回か通っているうちに、ちょうど九谷村の入り口は狭かったですよね。車一台やっと通れる、あそこに後藤才次郎の碑が建っていましたよね。あのでっぱりを削って、そして道路を広げる工事に入られたんですね。あの崖面を削り始めたときに、たまたまそこに通ったところ、白いところと黒いところがね、縦縞のように出てたんですね。あれはいったい何だろうかということで上ってみてみましたら、白い所は石灰分が多いものでしたけど、黒い所は、はじめは鉄が酸化したものだと思ったんですね。朱田があって朱石があって鉄がたくさんあることは分かっていますので、酸化すると本当に酸化せずにそのままあると黒くなっていきますので、たぶんそれだろうなとよく見てみると、赤みが全くないんですよね。これは崖面からとってきたものがこれなんですね。拾ったのが崖の下で、みんな削ってますから持って行って、どっかにダムの工事の枯れ淵あたりに原っぱを造ったりして、そこに並べて埋め立てているわけですよね、だから、拾って帰っても怒られないだろうと思って持ってきたのがこれなんです。
- 帰ってきてさっそくこの中ははじめの間どろどろですので、じゃーと洗って表面など捨ててたんですね。今思うと本当にものすごくもったいないと思うんですけどね、この中に詰まっているわけですね。これは、外は珪石(けいせき)なんです。水晶なんか一杯でていますけどこれをほじくりまわしまして、そして生成して、こんな細かいこんなものがでてくるんですね。これを乳鉢で粉砕しまして、水簸(すいひ)という順番に水を変えていって細かいのを集めていくわけですね。で、これがこっちからほじくりだした形がこんな形です。そしてこれが次に選別したものですね。これがその次に水簸して、一番最後のこれが呉須になるわけです。これに溶かす材料を入れますと現在の九谷のあの黒い線をひく呉須になるわけです。
- 実験したのは、これは升目に書いてありますね、絵の具の実験のひとつのパターンです。どんな場合でも、まずこの升目で実験するわけです。升目の間の濃淡とか、呉須がうまくできるかを全部これでやるわけですけど、で、やりますと、すごくきれいな真っ黒い呉須になるんですね。こっちの方は現在、私とか九谷の業者が、絵描きさんが使っている市販されている、能登呉須といわれる呉須といわれるもの、これを使って私仕事をしていたわけですけれども、これよりもこっちの方が使いやすいんですね。これは科学的に合成して能登呉須といってますけれども工場で作ったものですね。で、これは自然にあるわけですからいろんなものが混じっているわけです。だからよく伸びますし、色はクリアですし、落ち着きもありますし、で、呉須がいいと絵の具が綺麗に見えるんです。黒が悪いと色が悪くなるんです。これおんなじ絵の具ですけど黄色ひとつ見てもらっても鮮明度が違うんです。本当はね九谷の絵の具は、ほんとうは透明感があるわけではないんです。下に黒があるからすごく透明に見えるんです。黒が悪いとこうやって濁って見える。同じ絵の具なんですけど、呉須は古九谷の存在を証明するひとつの材料になるんですよね。どういうたらいいですかね。柿右衛門、伊万里にしても京都の仁清にしても皆この黒い呉須を使っていたわけです。だけどどこでそれを手に入れていたか不明なんですね、今のとこ分からんのですね。ご存知のように不明なんです。歴史で証明されていないんです。証明されていないから、中国から輸入したのを使ってたんでないか、それがなくなったんだから、絵を付けるのをやめたんじゃなかというのが定説ですよね。九谷には、足下にあったということです。今から350年前には。住んでいた人たち、あそこに鉱山がありましたからリンとか俗に鉄とか、砂鉄というものを掘ってましたから山を削っていますから、こんなものがあるのも分かるんですよね。
- 中矢進一氏 >
- それでは、楽焼き、押小路あたりとの和絵の具の関連、九谷焼との関連、そのあたりの話をしていただければと思いますが。
- 正和久佳氏 >
- 結局、赤もそうですし今の呉須もそうですけど、それを使ってそれ自体を混ぜる、それだけでくっつきませんので。結局呉須とかこうゆう赤を素地の白い所にくっつけるのりが必要なんですね。それを釉薬とか絵の具とか言ってるわけですけれども、それを、現在のところは白玉(しらたま)っていいましてフリット、私たちフリットを昔から白玉と言われまして、珪石と鉛をいっぺん溶かして鉛ガラスを作るわけですね、それを粉砕して粉状にしたものを使うわけです。その方がいっぺん溶けてますから、溶けなくていいわけですね。少し熱を加えますと緩みますから、緩んだらそれでガラス状になるからここにくっついてくれるわけです。そういうのを使うわけです。だけど、それはくっついただけで色にならない。色にならないというか、不透明な色に、こういう赤みたいに不透明な色になるんですね。で、こういう透明な色をつくるためには溶かさないといけないガラスにしないといけない。ガラスにするためにはフリットだけでは今度はガラスに早くなりすぎて流れていくわけです。力がないために、改めてもういっぺん珪石っていうのを加えてやるわけですね。珪石と白玉とで普通は透明な絵の具になるはずなわけです。今度は強くなりすぎて、欲しい温度ではとけないわけです。で、そのために、もう少し溶かすために、生の鉛を加えて結局、白玉と珪石と鉛の三つで、その三つに色の元になります、銅ですとかコバルトとか入れてやると溶けて、溶けた中にその細かい鉄とかマンガンとか炭酸銅とか浮遊しているわけですね。顕微鏡で観ますと細かい粒がばあーっとあるわけです。それが色を出しているわけですね。粒が大きければ色は違った色になるわけですけど、粒が小さいほど透明感のあるきれいな色になるわけです。
そういう絵の具にするための材料をいまのフリッターは白玉を使ったのをフリッター合わせ、白玉合わせというんですけど、それは白玉ができてからの話で、白玉というのをガラスを使うかっていう分かる以前は何をどうしていたのかっていう問題があるわけです。一番古い焼き物をつくる本として残されているのが京都の乾山という人が仁清から聞いたという形で残っているわけです。それは、一応印刷物になるのは現代に入ってからなんで江戸時代は誰も読むことはできなかった。じゃあ、どうして江戸時代の人はそれを知ったのか、まずそこから探し始めまして結局、奈良時代に瓦の職人がいて緑瓦というのは奈良時代にできているわけです。緑瓦というのは銅を鉛にとかして瓦に塗ったわけですね。銅を使って絵の具にする、塗るという技術はあったというわけです。人間のことですからいろんな工夫をしてきていますので、鉛ガラスの作りかたが派生してきて奈良三彩ができたんだと思うんです。あれは、鉛と現在は私の知る限りでは鉛と発色剤だけであると、だから不透明である。鉛だけではガラスになりませんからね。必ず珪石がいりますので。
そういう流れからずーっと中世を通り越しまして近世に入って江戸時代になったときに、豊臣時代もひっかかるんですけど、利休という人がでてきまして、瓦職人だっといわれている朝鮮から来た人に、楽焼という焼き物を作らせるんですよね。今でこそ楽焼と磁器とは区別していますけど、豊臣時代ぐらいまでは釉薬のかかっていた焼き物は茶碗と呼ばれていたんです。今でいう磁器とか壷とか、なんとかいっぱいいいますけどそういう区別はなくって、日本には釉薬がかかった焼き物ってありませんでしたので、釉薬のかかった焼き物は全部唐渡り、中国、朝鮮。日本で初めて上薬がかかった焼き物ができたのは楽焼きなんです。だから、ものの本によりますと磁器って書いてありますよね、楽焼きを。そうゆう感覚だったんですよ。当時はフリットっていうのはありませんから、生で、生っていうのは変ないいかたなんですけどフリットを使わない釉薬が開発されたということですね。それが初代、二代、三代くらいまでの釉薬に楽焼きの上薬に使われていた材料合わせだってことですよね。その材料合わせの、どうしてそれが世の中に広まって、いろんな人が一家相伝であるとか秘宝ってかたちで伝わっています。たまたま私、京都にクラフト世界会議っていうのがありまして、そこに行きまして、先代の14代楽吉左衛門さん、【覚入】とおっしゃる方にお会いしてお宅に訪ねました。窯場であの方が作っておられまして、楽の話を聞かせていただきました。その時に、私も楽焼を作りたくなったので「作ってもいいですか」と聞くと、だいぶ考えられておりまして、「いやー難しいですよ、それ承知なら作ってみなさい」って。帰ってきて早速つくり始めたのがこの楽焼なんですよね。
- その時におっしゃったのが「始めは今みたいにフリットというのは使わないよ、全部生の材料を合わせて使ってたんだよ」、ということをおっしゃって、で、たまたま、帰ってきてその話を高陶岳という方がおいでまして、私が、九谷焼にはいった時の最初の先生だったんですが、その方に話したら、「あるよ」って、簡単におしゃって、「え!どこにある」、「家にあるよ」、っておっしゃって「ずっと昔から家に生で合わせる調合が残っているよ」、ノートをみせていただいてここにあるって。「先生、これで絵の具になるんですか」って聞いたら、「なるよ、ちょっと難しいけどなるよ」っておっしゃって。やってみたらやっぱり絵の具になるんですね。すこし温度は高くいりますけど。普通のいま九谷焼は大体750°、600°〜800°で焼いておられるけど、それでは無理で850°まで上げないと透明なものになりません。で、その今、ちょうど1700年前後くらいに楽焼を作る本がでてるんですよね。それを見つけまして、「一般に公開されてるじゃないか」っていう思わず言ったんですけど、その古九谷時代はやっぱり生でないと、あの盛り上がりがでない、フリットはガラスでやっぱり薄くなっちゃうんですよね。どうしても生で合わせますと薄くなっちゃう、材料が全部もとのままですから盛り上がるんです。楽焼の厚みも、たらっとかかるわけですね。それをつくるためには珪石と鉛、基本はこの2つしかありませんので、いい形の珪石と形いい鉛がいるってわけです、鉛はもう石川県、加賀藩にありましたからね。鉛いっぱい掘ってますし、金沢ではお城を造っていましたしね。その材料も九谷にもあったということなんです。
これがその珪石なんですね。これかなり風化してますので非常に壊れやすいんです。金槌でたたくとぼろぼろ壊れていきます。普通珪石や石英になると、ちょっとやそっとじゃ壊れないんですね。ある一定の方向には壊れますけど、これは粒状に砂になっていくんです、これから硅砂(けいさ)っていう砂状、細かいお米みたいな感じになっているわけです。これが風化していきますと、こういう形になるわけです。これが陶石ですね、これを粉砕して焼くとこういう焼き物になります。これは九谷でとってきたものです、まだ大きいものがあるんですが、拾ってきた。これ結構汚れていてこれだけだと純度が悪いんで、汚い焼き物しかできませんが結局こういう形のものがこうなっていくわけです。すんごい時間がかかるんですね。これに鉛を少し混ぜてやりますとこうゆう透明な、この黄色い色はこれは土の色です。それからこの白っぽいこれはこの珪石を溶かさずにおいてあるわけです。上にたらっとなるのは溶けた部分で、真ん中に残っているのは長石質と珪石質といわれているんですが、長石だと志野みたいにぼたっとして割れていくわけですね。珪石ですと、なじんでますから中にとけない部分が中に残って、溶けた部分が表面を覆っている、そんな感じになるわけですね、それが生で合わせる特徴ですね。で、ここにこれに色絵の具に使うと下に、黒い呉須がくっきり浮かび上がって上に色素の色がでて、そして濁っていても透明感が生まれるという。古九谷のあの絵の具でも、透明度とか絵の具の質とか調べて、分析してですね。絵の具の質を九州と京都と比べられるともっと面白いという気がしますね。で、珪石はあるし絵の具の色になる材料はあるし、あとは鉛さえもってこれば九谷で全部できるという、どっからでも輸入しなくても集めてこなくても。ただないのはコバルト系のものですから。だけどコバルトは九谷のあの窯跡から、染め付けがいっぱいでてきてますからね。彼らはちゃんとコバルト、呉須を持ってましたから、それで紺青はでますから全部揃っているという。どっからも買わなくていいという。しかもただですからね、足下にあるわけですから。で、それで今度は絵の具の発見、ダム工事と吉田屋の発掘の二つの余計っていいますかね。九谷焼を研究するものにとっては大変なものを頂いたなという。
 |
 |
 |
||
| 収録ビデオ画面より | ||||
 |
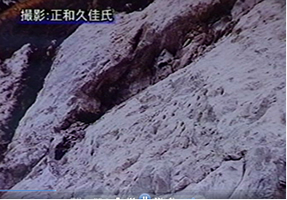 |
|
| 収録ビデオ画面より | ||
 |
 |
|
| 収録ビデオ画面より | ||
 |
| 収録ビデオ画面より |
 |
| 収録ビデオ画面より |
 |
 |
|
| 収録ビデオ画面より | ||
対談終了
- 司会 >
- 小松市立博物館専門委員の正和先生のVTRでした。正和先生はやはり実際に制作されている、なさってる方ならではのご意見をお持ちですね。
- 中矢進一氏 >
- そうですね、例えば楽焼きの釉薬との共通点だとか、なんといっても黒の絵の具、九谷呉須ですね、原料の発見これはまことに画期的なものだと私も思います。そのあたりの詳しいいきさつに関しては前にも紹介しました、「陶説 618号」の九谷特集の中で正和先生が詳しく書いておられるのでご関心のある方は是非ご購読をいただければというふうに思います。