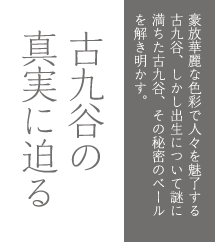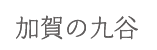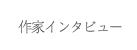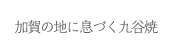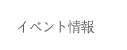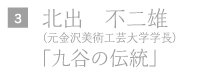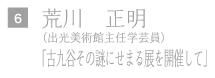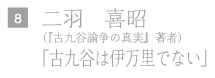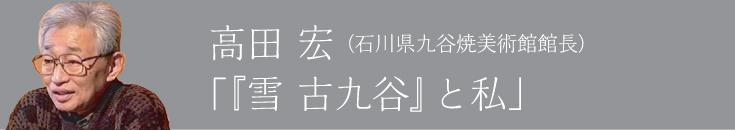
- 司会 >
- 今回は、石川県九谷焼美術館館長の高田宏先生にお話をお伺いいたします。中矢さん、高田先生は加賀市の九谷焼美術館の館長さんでいらっしゃいますね。
- 中矢進一氏 >
- 私どもの館長をしていただいています。
- 司会 >
- 先生には、どのようなお話をお伺いしていただいたんでしょうか。
- 中矢進一氏 >
- そうですね、先生はこの小説『雪 古九谷』をお書きになっておられるんですが、この『雪 古九谷』をお書きになられた上でのいろいろなエピソードみたいなものを中心に、お話を聞けると思います。
- 司会 >
- それでは、石川県九谷焼美術館館長の高田宏先生には、先生の著書であります「雪 古九谷」について、お話しを伺っております。VTRをご覧ください。
対談
- 中矢進一氏 >
- 高田先生の著書の中に、ここにもありますけども『雪 古九谷』という小説がございますが、この小説を書かれるきっかけと申しましょうか、それはどういうことなんでしょうか。
- 高田宏氏 >
- これは、もうずいぶん昔のことですけど、20年も前かな金沢の県立美術館の古九谷の展示室に入って、前から観ていたものもあったんだけども、その日出ていたのがそれまで観たことのなかった、あの「青手桜花散文平鉢」という、あの県立美術館では名付けている作品ですけどね。今、僕なんかは中矢さんもそうですけど「青い桜」といった方がとおりがいいんだけど、それの前に来て、本当に文字どおり足が止まったのね。動けなくなって、“凄いものがある”それまで、古九谷の持っている力には、かなり惹かれてはいたんだけど、もうそのレベルが違うんだね。本当にそれまで学生時代から、たとえばピカソ展とか、ゴッホ展とか、ルオー展とか、マチス展とかいろんなものを見て、それなりの感動はしてきたんだけど、その「桜花散文平鉢」これを観たときには、そういう全ての世界の絵画の名作を観た感動を突き抜けてましたね、それ以上だった。
ところが、これは古九谷だから作者不明でしょう、だれが作ったか分からないけれど、目の前にものがあるわけね、確実にこれを共同作業で、絵のある部分をだれか、ある部分をだれかやったとはとうてい思えない。1人の人間があの絵付けをやっている。つまり焼物では絵付けといっても、あれは1つの見事な絵画作品だと思うんですよ、直径45㎝の大きな平鉢の全体を絵画でいうキャンパスとして使っている。そこに1人の天才画家が見事な作品を描いて、しかもそれは自然を写生したというわけではない、写生ではないけれども自然の本質を一気に掴み取って、直径45㎝の丸い画面の中に宇宙がとらえられている。それから無限の時間がそこに閉じ込められている。そういうものは、生半可な画家ではできない、すごい仕事ですよ。それでびっく仰天して誰がどんな男が、もちろん記録もなにもないけれども、どんな人間が男と言ったけど、女かもしれないですよ。でも男としてこの「雪 古九谷」の中に書いたけれども、どんな人間がこれを描くための、すごい美意識を自分の中に育てたんだろうかという、その疑問を解くためにいろいろ調べもしたけれども、しかし古九谷に関しては、文献はごく少ないですからね、だからほとんどは、わずかな文献を外さないようにしながら想像の産物ですけれども、いろいろ一種の推理をやっていく中で、これはもう確信を持って、間違いないという所に、到達できたと自分では思っています。
そのために古九谷の窯跡にも行きましたよ、それも雪の時季に山中温泉から九谷の窯跡まで、結構な距離あるけど、そこを雪の中を歩いたんですよ。一緒にいった編集者がくたびれはてて、もう僕はまだその時50位かな50過ぎかね、まだ体力があったんだね。若い編集者はへたばって最後に旅館の階段を登れないほど、ばてたんだけど。山中温泉から何里も奥の、あの大聖寺川に沿っていく、その雪の風景がやっぱり当時の世界の中でも信じられないような、美意識を生む大本だったと思いますね。
- 中矢進一氏 >
- ただ今は、『雪 古九谷』の小説を先生が書くひとつのきっかけのような、このお話を聞かせていただいたんですが。それでは次にそのいわゆる北陸加賀という土地、そしてそれから風土と申しましょうか、そういったものと、この古九谷いわばその跡を継ぎました吉田屋等の九谷焼について、先生の思いと申しましょうか、そういうものをお聞かせいただけたらと思います。
- 高田宏氏 >
- さっきの話にも出した、青い桜ですね「青手桜花散文平鉢」、これ「青い桜」というのが、実はNHKの命名なんです。NHKの新日曜美術館でこの石川県九谷焼美術館を大きく取り上げて下さって、その中でも、「青手桜花散文平鉢」が主役として扱われ、タイトルも実は「青い桜」というタイトルの45分番組になったわけです。その「青い桜」に非常に顕著なんだけども、これはもう大自然と直接に向き合っていた、つまり自然の本質と人間とが向き合ったときに初めて生まれてくる美意識だと思います。たとえば、いろいろな様式美の伝統があって、そこから勉強してとか、中国の絵画の伝統から学んでとか、そういう間接的なもんじゃなくて、描き手が生に接している大自然、その本質をその人の天性で掴み取って描いたそうとしか思えない。そのためには、何が必要かというと、僕はここに書いたのは、一つは従来の世の中にある美意識に汚染されないように、そのために後藤才次郎っていう男が大変なプロデューサーだった。アートデレクターというのかな、それから自分は実作者じゃないけれども自分が育てていく絵付師、画家の中にあるものを伸ばしていく力、そのために才次郎はその若い青年に「いろんな他の人の描いた絵を観るな」と、「自分で自然と直に向き合ってその向き合っている中から掴み取れ」と、そういう意味でのアートデレクションをしていた。たぶん、後藤才次郎というかなり風変りな侍、殿様からは「ありゃちょっと偏屈者だから」と言われている高慢ちきな、高慢者でなかなか下っ端の侍のくせに殿様の言うことを聞かない、そういう変な男、しかしその変な侍だからこそ世の中にある普通の美意識からきれいに切断した形で、一切そういうものの影響を受けない、汚染されない、この九谷の山奥での自然と向き合って美意識を生み出すことができたんだと思う。それに答えた人間がいた、若者がいたという。それが僕の考えなんだけれども、だから一つには古九谷の中にも、もう少しこうお手本にならったようなものも実はありますよね、それは僕はむしろ絵付けは僕の考えでは、大聖寺城下にあった藩邸のどこか周辺に上絵窯があって、九谷で焼いたものを、あるいは場合によったら伊万里から移入した素地とか、そういうものを含めてある程度伝統的な美意識を持っているような、いわばプロの絵描きに絵付けをさせている。
それともう一つは、それと無関係に九谷の山奥でたとえばちょっとした、ヒビが入ったりして、あまり出来のよくない素地そういうものを後藤才次郎が青年画家に命じてこれを自由にやれと伸ばしていこうとした才能を開かせていったんだと思いますね。
九谷に行ってみると分かりますけれど、あそこは今でも冬場大変、今はダム用の道路ができてずいぶんよくなってるようだけど、それでも雪が深く積もってしまうと九谷まで行くのは楽じゃない、まして昔はそんな道がないわけだし、完全に孤立していたんです。だから、窯場のいろんな仕事をしていた人達の大半は冬が来る前に里へ下りたはずです。また雪解けを待って山へ上がっていく、でも九谷の村に残っていた、そういう人間も数少ないけれどもいて、その中に天才画家に育っていく青年がいた。その時に九谷で雪に覆われて山中温泉まで行こうと思ったって無理といった。そういう孤絶した世界ですよね、そこに生まれてくる本当に大自然と直に向き合った非常に骨太でそしてピュアな意識ですね、これが生まれることが可能だった。
そして、その後は古九谷もいろいろ変遷してきますけれども、殿様代わったり、それからいろいろと窯の管理者も代わってきます、代わって行けばそれなりに、もう少し平凡なものになっていく、そういうきらいはありますね、平凡というか特に普通の美意識から完全に飛び離れたものというのは、周りの人には分からないです。もうちょっと分かりやすいものになっていく方向もある。と同時に古九谷の残してくれた、その自然と直接に対話をした。奥行きが深くってエネルギーに満ちた、その仕事を後世の人が、100年たち、200年たちその後世の人が「あれはやっぱりすごい」と本当にいいものは人の心を時代を超えて打つんだなと思っています。
その打たれた人の中に吉田屋窯を作った豊田伝右衛門といった人がいたわけであります。特に古九谷の中でも「青い桜」もその1つに分類されている青手の古九谷っていうのをこれこそ古九谷だと古九谷の本当の精髄だといって、吉田屋窯はその美意識を受け継いで、再現というかその美意識の上に立って新しくまた焼き物を作りだしていったわけです。だから一番大本にあるのは、やはり雪深くてそして雪解けになれば一気に春が、若葉が芽吹き、若草が生えてくる、そして花が開いてくるといった。その雪解けから春への季節のドラスチックな大変化があったり、そしてとりわけ平地以上に四季の変化が鮮やかでしょう。雪の深い世界というのは、そして深い雪の中で今度は精神的にずうと集中している時間がある、そういうサイクルの中で、古九谷の名品は作られてきたと思うし、そして古九谷の名品の中の真髄を吉田屋は受け継ごうとしたんだと思う。
そういう意味では雪国ならどこでもよいかもしれませんけどね、さまざまな条件がありますからね、殿様が窯業を興そうと考えたとか、いろんなことが歴史的な条件がありますから、それから後藤才次郎のような名プロデューサーがいたかいなかったかとでは、全然違うしだからどこの雪国でもできるというものでもない、やはり城下から非常に遠く離れた、冬場は完全に交通途絶、別の時間が流れている、そういう世界があったからこそ、そしてまた世界が春になると一気に別の世界に変わっていくその条件が満たされて始めて古九谷は生まれたんだと思いますね。古九谷の中のとりわけ青手は。色絵の方は、これはいろいろと直接に自然と向き合わなくても、ある意味で伝統的な日本の中国の美意識をその上に立って自分なりの工夫をしながらやっていくことは、可能だと思っています。青手の中の全てとは言いませんが、かなりの部分はそこからじゃ生まれてこない、あくまで土地と結びついたもので、だからね、よく言われている古九谷伊万里論だけれど、初期伊万里といったりするらしいだけど。どうして、あそこにそういう美意識はかけらもないではないか、もっと様式化されたもの、そして従来の周辺にある美意識と深くつながっている。伊万里というか有田には、他と無関係に生まれてきたようなそういう美意識じゃないですよ。最初に言った「青い桜」は一点見たってあまりにも歴然としている、「青い桜」は伊万里の伝統美意識の中に生まれてくるはずがない、またそういうものをあれも初期伊万里とか伊万里の古九谷様式だとか言おうとするのは、言うも愚かなばかばかしすぎて、論争するきにもならない。どうして、たとえばピカソとゴッホが違うということすら分からないような意識でしかないんじゃないかという、そういう気がしますね、だから古九谷とりわけ九谷焼全体の中で、古九谷しかも青手古九谷は、ぼくはこれはすぐれて絵画だと思いますね。たまたま、描く場所が磁器の上だったわけで、作品の本質としては絵画作品だと思っています。
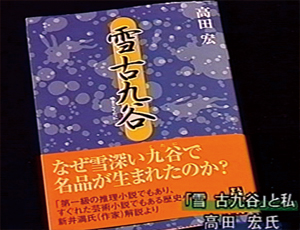 |
| 収録ビデオ画面より |
 |
| 収録ビデオ画面より |
対談終了
- 司会 >
- 中矢さん、高田先生は「青い桜」といわれております「青手桜花散文平鉢」こちらに非常に感銘を受けて、小説をお書きになったということでいらっしゃいますね。
- 中矢進一氏 >
- そうなんです、つまりこの北陸加賀という、この土地、その風土とかから、それを背景にして生まれた古九谷、つまり古九谷の精神性と申しましょうか、そういったものに焦点をあてた、お話だったというふうに思います。その精神性を受け継いだのが江戸後期の再興九谷の吉田屋といったようなことであろうということも述べられておりましたね。